現代のインターネット社会を支える「暗号技術」。でも「暗号ってなんだか難しそう」と感じていませんか? この記事では、初心者の方でもスラスラ読めるように、古代から中世までの暗号の歴史を丁寧に解説します。紀元前のスキュタレー暗号から、ローマ帝国のシーザー暗号、そして日本の戦国時代に使われた武将たちの秘密通信まで、時代ごとの暗号の知恵と工夫をたどっていきましょう。
暗号の原点:スキュタレー暗号とシーザー暗号のしくみとは?
🔸紀元前500年、古代ギリシア・スパルタ軍の知恵 紙をらせん状に巻きつけ、棒の太さを“鍵”にしてメッセージを隠すシンプルな方法ながら、敵に読まれにくい工夫が詰まっていました。

こんな昔から「鍵」が使われていたなんて驚き!

そうなんだよ!今の暗号と同じで、鍵が合わないとメッセージは読めなかったんだにゃ
🔸ローマ帝国・カエサルの秘密通信 アルファベットを一定の数だけずらして暗号化する「シーザー暗号」は、暗号技術の原点として今も学ばれています。

でもずらすだけならすぐ解けそうだよね?

その通り!でも「暗号をつくる」って発想自体がすごかった時代なんだよ。
➡️ 詳しく知りたい方はこちら:【古代の暗号史】スキュタレーとシーザー暗号からはじまる情報防衛の物語
戦国武将の情報戦:上杉謙信と武田信玄
🔸日本独自の暗号文化の幕開け 上杉謙信は文字を別の文字の組み合わせに変える「換字暗号」を使い、武田信玄は手紙の中に隠しメッセージを埋め込む“忍びの暗号”を活用していました。

まるでスパイ映画みたい!

その知恵が今の「ステガノグラフィー」や「認証技術」にも通じてるんだにゃ
➡️ 詳しく知りたい方はこちら:戦国時代の暗号とは?上杉謙信・武田信玄が使った秘密通信の技術を徹底解説
中世の数学が暗号の精度を変えた:擬素数とカーマイケル数
🔸フェルマーの小定理と数学的暗号の夜明け 素数の判定に使われる数論知識が発展した中世〜ルネサンス期。フェルマーの小定理や擬素数の存在が、暗号の精度に大きな影響を与えるようになります。

えっ、「素数かどうか」を見抜くのが暗号の基礎なの!?

うん、それを誤魔化す“そっくりさん”のカーマイケル数には要注意にゃ!
➡️ 詳しく知りたい方はこちら:暗号の変遷:中世からルネサンスへつながる数と知恵の進化史
数学と暗号が交差した瞬間:フェルマーの最終定理
🔸数学界の伝説が、現代暗号の土台に ルネサンス期の自由な数学的探究は、やがて楕円曲線理論へと進化し、現代のECC(楕円曲線暗号)へとつながっていきました。

歴史ってちゃんとつながってるんだね…!

うん、中世の数学好きたちが、今のセキュリティを支えてるんだにゃ
➡️ 詳しく知りたい方はこちら:中世〜ルネサンス時代の暗号手法の変遷
まとめ:暗号のルーツは驚きに満ちている!
今回ご紹介した内容から見えるのは、「暗号の歴史=情報を守る知恵の歴史」だということです。
🔹 スキュタレーやシーザーの単純な工夫が、暗号文化のはじまり 🔹 日本の戦国武将たちが創意工夫で情報を守った 🔹 中世の数学が、やがて現代暗号理論に直結した
これらの知識を理解しておくと、暗号の未来を考える上でもとても大切な視点が得られます。
➡️ 次に読みたい記事はこちら:戦争が進化させた暗号技術:第二次世界大戦から現代へ
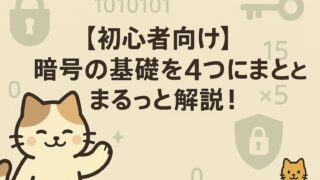
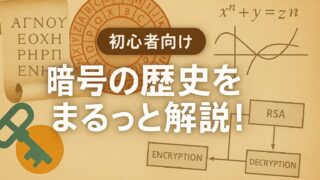


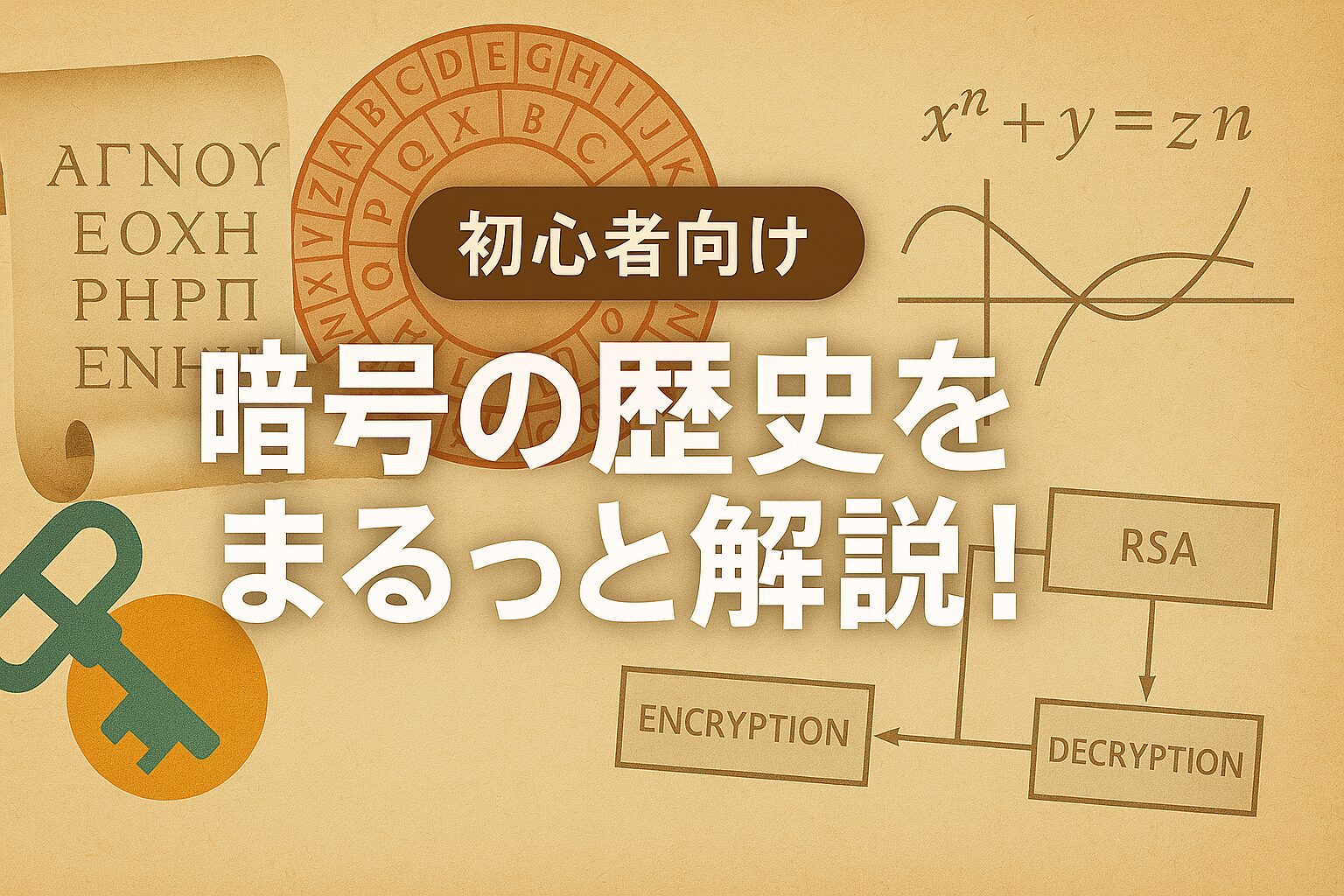
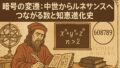
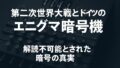
コメント