戦国武将たちも使っていた!「暗号」のはじまり
スマホやインターネットが当たり前になった現代。誰もが「暗号=ネットセキュリティ」というイメージを持つでしょう。でも実は、暗号はずっと昔、戦国時代の武将たちも活用していた重要な技術でした。
例えば上杉謙信や武田信玄といった名だたる武将たちは、戦の勝敗を左右するような極秘の命令や情報を守るために、自分たち独自の暗号方法を生み出していました。
この記事では、そんな戦国時代の「日本初の情報セキュリティ術」ともいえる暗号技術と、その後の進化がどのように現代のネット社会に受け継がれているのかを、もふねこと一緒にわかりやすく見ていきましょう。
🏯 上杉謙信の「換字暗号」:誰にも読めない戦国の秘伝書

上杉謙信って、あの越後の龍?戦が強いだけじゃなくて、暗号まで使ってたの?

そうにゃ!実は“換字暗号”っていう特別なルールを使って、敵に見られても意味がわからないようにしてたんだよ!
上杉謙信が使っていたとされる暗号技術の中でも有名なのが「換字暗号」。これは、特定のひらがなを、あらかじめ決めておいた別の文字の組み合わせに置き換える方法です。
🔐 暗号の具体例
- 「あ」→「をな」
- 「い」→「すめ」
- 「う」→「こみ」
というように、味方だけが知っている“暗号表”を元に書かれた手紙は、敵に見られても全く意味がわかりません。これにより、伝令が捕まっても作戦がバレない仕組みをつくっていたのです。
こうした方法は、現代の「置換暗号(substitution cipher)」の原点とも言えます。
🕵️♂️ 武田信玄と忍びが使った「隠し暗号」

信玄は、ただの文字の入れ替えじゃない“見えない暗号”も使っていたんだにゃ

見えないってどういうこと?
武田信玄は、“忍び”(スパイ)に命じて、敵陣へ情報を届けさせていました。その際、普通の手紙に見せかけて実は中に秘密のメッセージを埋め込むという「隠し暗号」を使っていたとされます。
📜 暗号の工夫
- 一見、普通の礼状や詫び状に見える文面
- 実際は、文章中の特定の位置の文字だけを拾うことで意味のあるメッセージになる
- 読み手だけが知っているルール(例:1行目2文字目→2行目3文字目…)に従って読む
これは現代で言う「ステガノグラフィー(情報隠蔽)」に近い発想であり、伝える相手が鍵(読み方のルール)を知っていなければ、内容を復元することはできませんでした。
🔄 シーザー暗号やエニグマとの比較:日本の暗号は優れていた?

外国にも似たような暗号ってあったの?

もちろん。ローマやドイツでも使われてた。でも、日本のはちょっと違う工夫があるんだにゃ
たとえば、古代ローマの「シーザー暗号」はアルファベットを一定の文字数ずらすだけの単純な方式でした。HELLO → KHOOR のように、暗号としての強度は低く、すぐに総当たりで破られてしまいます。
一方、日本の戦国暗号は“複数文字への置き換え”や“隠蔽式の情報構造”など、初歩的ながらも解読に手間がかかる工夫が施されていた点で、実用性が高かったといえます。
さらに第二次世界大戦の「エニグマ暗号」は、毎日変わる複雑な設定と数兆通りの鍵が特徴でしたが、それでもアラン・チューリングたちによって解析されました。
日本の武将たちは、技術の進化とは別の“創造的なアナログの仕掛け”で暗号を扱っていたのです。
🔑 現代の暗号とつながる「鍵」の発想

現代のインターネット暗号も、鍵がなければ読めない仕組みにゃ

えっ、じゃあ戦国時代の暗号と同じ考え方ってこと?
そうなんです。現代の暗号方式(RSA、AESなど)でもっとも重要なのが「鍵」です。どんなに複雑な方式で暗号化しても、その鍵が第三者に知られてしまえば、すぐに中身は読まれてしまいます。
上杉謙信の換字暗号では「暗号表」が鍵。武田信玄の隠し暗号では「文字を拾うルール」が鍵でした。これらは“情報を守るために、何かを共有しておく”という鍵管理の本質を、戦国時代の時点で体現していたといえます。
現代では、その鍵の桁数を増やし、数学的な理論に裏付けられた方法で守っているに過ぎません。思想のルーツは同じなのです。
🧭 暗号の進化:歴史から未来へ

古い技術が、こんなにいろいろな場面で活かされてるなんて意外だなあ

時代を超えて“情報を守る心”がつながってるんだにゃ
古代ローマのシーザー暗号から始まり、戦国の換字・隠蔽技術、そして第二次大戦のエニグマ暗号を経て、現代のRSAや量子暗号へと、暗号は進化を続けています。
共通しているのは、どの時代も“情報を読まれたら終わり”という切実な現場のニーズと、「誰に伝えるか、どうやって伝えるか」を工夫する人間の知恵です。
未来では量子力学に基づく通信が主流になるかもしれません。でもそこにある思想は、戦国の武将たちが命をかけて守った「あの暗号」と、驚くほど変わっていないのです。
🎯 まとめ:戦国武将が残した「情報防衛」の知恵
- 📌 上杉謙信は「換字表」を用いた暗号で作戦を秘匿
- 📌 武田信玄は「隠し文字」で敵に悟られない通信を確立
- 📌 鍵の概念は、現代のRSAやAESにも引き継がれている
- 📌 暗号の思想は、古代から現代まで一貫して「情報を守る工夫」

戦国の知恵が、今のデジタル社会の安全を支えているにゃ!情報を守るって、昔も今も、変わらず大事なことなんだにゃ〜
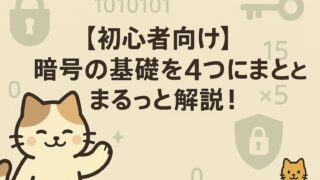
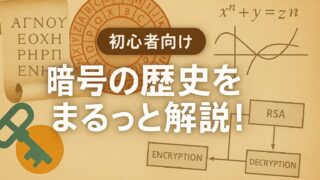




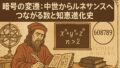
コメント